がんばれ!図書委員
ソフィアセンターでは、学校図書館で頑張る図書委員の皆さんを応援しています。
ここでは、図書委員として知っておきたい基本や学校図書館の読書環境をよくするためのコツを教えます。
図書の分類
たくさんある本の中から、読みたい本をさがすとき、どうしたらいいでしょうか?自分の家の本棚なら大体の見当がつきますが、図書館のようにたくさんの本があって、多くの人が利用する場合、きちんと整理されていなければ、読みたい本にたどりつきません。
そこで図書館や図書室では、同じ種類の本は同じ場所に集めて、目的の本にたどりつくように分類しています。この分類は基本的に「日本十進分類法」を使って行います。
日本十進分類法とは、種類を大きく10に分け、この作業を繰り返して、だんだん細かく分けていく方法です。
最初の区分を類(るい)といい、綱(こう)、目(もく)と続きます。これが本の住所になります。
『ソフィア鳥の研究第1巻』 柏崎太郎/著の分類番号は?
「鳥」は4類自然科学に属することがわかります。4類自然科学・医学を10に分けてあてはめると48(よんはち)の「動物」に当てはまります。48動物を10に分けると、488(よんはちはち)の「鳥」に当てはまります。
したがって、この本の分類番号は「488」となります。

本のラベル
本の「背(せ)」に「ラベル」が貼られていますね。
日本十進分類法を使って分類した本は同じ種類のものは同じ分類番号になります。
そこで同じになったものをより細かく分けるために、図書記号(著者記号)や巻冊記号をつけ、それをラベルにして貼ります。

『ソフィア鳥の研究第1巻』 柏崎太郎/著のラベルは?
『ソフィア鳥の研究第1巻』 柏崎太郎/著のラベルは、次のようになります。(図書は著者名から1文字とっています。)
これがこの本の住所です。

配架
本を並べることを配架(はいか)といいます。本を棚(書架)に並べる際に、次のように並べると利用しやすくなります。
- 本は、いちばん上の段から並べる
- 棚には、左から右へ並べる(分類番号小さい方から→ 図書記号のあいうえお順)
- 2、3冊入れらるところでやめる(本をつめすぎない)
- いちばん右の本のとなりにブックエンドを入れて、本がたおれないようにする
- 大きくて厚い本は安全面を考え、下の棚に入れる(赤い矢印の部分です。)
- 最後に本の背を揃え、タイトルが見えるようにしましょう。

書架の下まで行ったら、上へ。上の段の左から右へ並べます。大きい本(赤の矢印)は大きい本だけで並べます。
本の修理
どんなに大切にしていても、形あるものはいつか壊れます。それでも、直せばまだ利用ができるものは、長く使いたいですね。それは、学校図書館の本も同じです。「ちょっと直せば読める」本は修理をして、また利用できるようにしてはいかがでしょうか。
修理の基本は「なるべく簡単な方法で」「できるだけ元の形に近く」「劣化しにくい材料を使って」「読みにくくならない」です。
ここでは、柏崎市立図書館の修理方法を紹介します。修理の方法は様々な方法があります。あくまでも参考にしてみてください。
セロハンテープでの修理はNG!


セロハンテープで修理をすると、数年後にはセロハンテープののりがべとつき、乾燥して茶色っぽく変色します。
そうなると、セロハンテープがはがれ落ち、変色した部分が紙に残ってしまいます。同じ理由で、クラフトテープやガムテープ類も本の修理には使いません。
セロハンテープで修理しないでください!
読み聞かせ
読み聞かせをしてもらうと、お話の世界に入りこんで想像もふくらんで、とてもわくわくしてきます。
また、「そうか!」「なるほど!」と新たな発見もあるでしょう。
聞き手にとっては、とても楽しいことばかり。
ところが、自分が読み手になったとしたらどうでしょうか。
大勢の前で声を出して読む…急に不安や心配が出てくると思います。
でも心配はいりません。ちゃんと準備をすれば大丈夫です。
まずは本を選ぶ(選書)
一人で読むときには良い本でも、大勢に読むには向かない本があります。
遠くから絵がよく見えない絵本、マンガのようなコマ割りの本、図鑑は読み聞かせに向きません。
次の選び方を参考に決めましょう。
- 学年や年令に合わせた内容と長さの本にしましょう。
- 行事や季節に合ったものにしてみよう。(12月ならクリスマスなど)
- 少し遠くても、絵は見やすいかな?
- 自分で読んでみておもしろいかな?
- 絵本を持ったとき、字は読みやすいかな?
- 1ページの文章が多くて長くないかな?
- 絵本を持ったとき、グラグラしないかな?
- 自分が「読み聞かせしたい!」と思えた本かな?
選書に困ったら、昔から長く読み継がれている絵本がオススメです。
必ず下読みをしよう
何かを発表するとき、大事な試合に出るときなど、その日が来るまで繰り返し練習をすると思います。読み聞かせもそれと同じです。
読む練習のことを「下読み(したよみ)」といいます。必ず下読みをして、当日に臨みましょう。
下読みをするときには、「ゆっくり」「はっきり」「大きな声」で読みましょう。また、絵本がグラグラゆれないように、絵本の持ち方も練習してみましょう。
絵本の読み方
- 表紙を見せ、絵本のタイトルを読みます。(作者名等は読まなくてもよいです)
- めくるときはゆっくりと。声ははっきり、後ろの席まで聞こえるように。
- お話を読み終えたら裏表紙までしっかり見せて、その流れで表紙も見せ、おしまい。 (読み終えた後の余韻を楽しみましょう)
絵本の持ち方

- 姿勢を良くしましょう
- 絵本の真ん中を持ち、片方の手で絵本の角を押さえます。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 図書館 サービス係
〒945-0065
新潟県柏崎市学校町2番47号
電話:0257-22-2928/ファクス:0257-21-2936
お問い合わせフォームはこちら





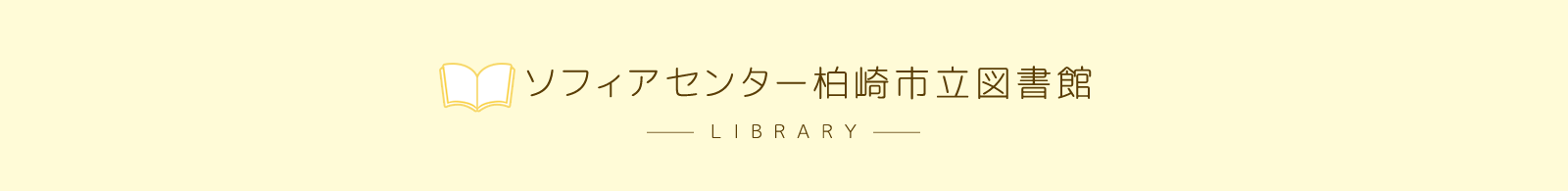
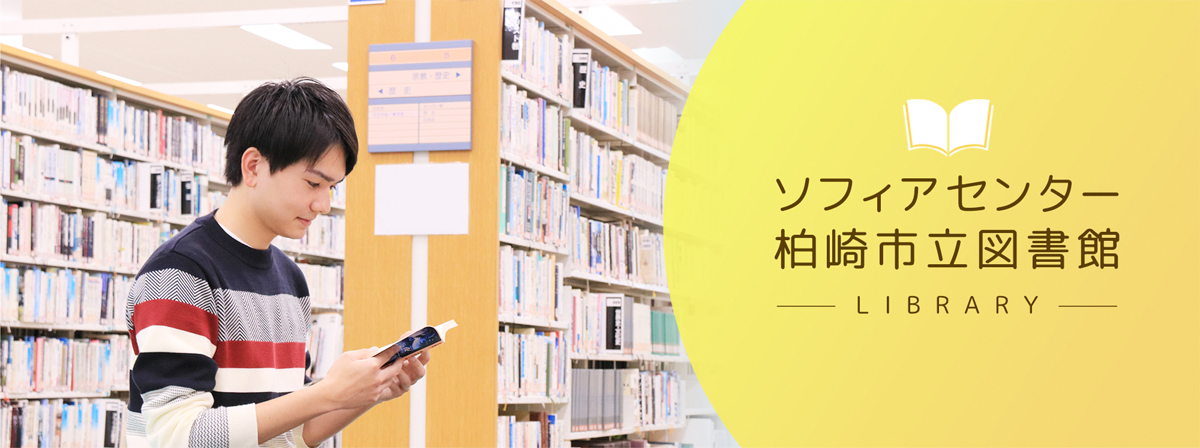

更新日:2020年02月27日